Scroll
海抜865mの六甲山頂付近に位置する当植物園は、
冷涼な気候を生かして、世界の高山植物や寒冷地植物、六甲自生植物、山野草など、約1,500種を野生に近い状態で栽培しています。
雪を割って開花する早春の花々や、初夏の新緑、秋には紅葉が園内を彩るなど、四季折々の自然・景色をお楽しみください。
植物にちなんだ雑貨屋さんや、カフェも併設しています。
















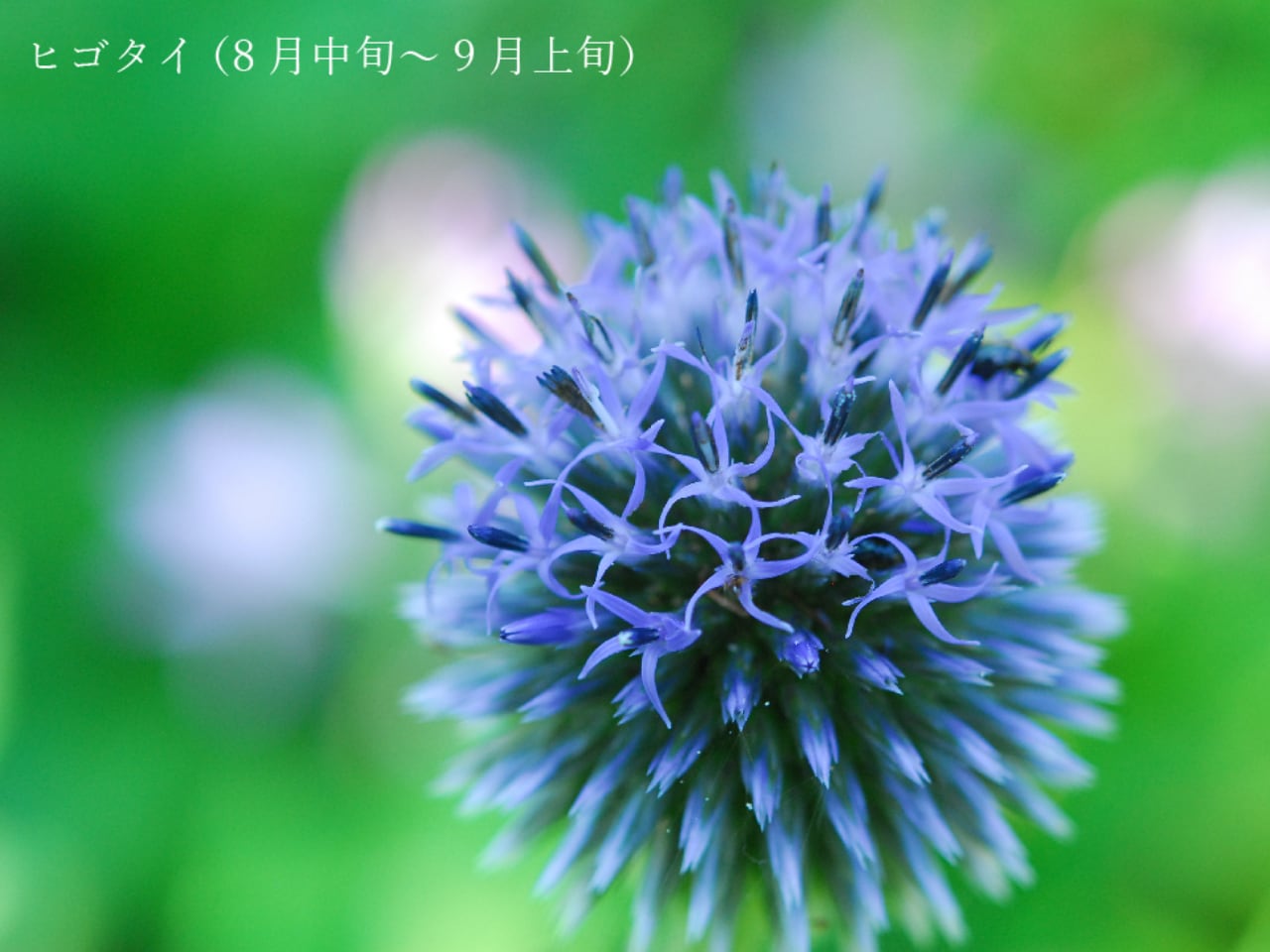





ロックガーデンとは高山植物を平地で楽しむために造られる造園形式のひとつです。高山の岩場の風景を模し、自然に近い状態で高山植物が観賞できるように工夫されています。高山帯に比べ、温度、湿度の高い平地で高山植物を栽培するために、特に水はけ、通気性が重視されます。
高木が立ち並ぶエリアです。次々に芽吹く新緑、夏の涼しい木陰、錦絵のような紅葉と、季節ごとに様々な景色を楽しむことができ、森林浴にもおすすめです。また、春には「カタクリ」、梅雨には「ササユリ」など、林床に生える里山の花々を鑑賞することもできます。
六甲山周辺にはかつて大小さまざまな湿地が点在していましたが、開発によりその多くが失われました。このエリアでは「サギソウ」など、六甲山の湿地に生息する貴重な植物を栽培しています。また、5月下旬に見ごろを迎える「クリンソウ」の群落は当園の人気のスポットの一つです。
東入口入ってすぐの斜面に、色とりどりの花々が咲き乱れる、高原のお花畑をイメージして約50種類の植物を栽培しています。ユリの女王「ヤマユリ」や絶滅危惧種の「ヒゴタイ」、キンポウゲ科の「サラシナショウマ」などが、夏~秋に見ごろを迎えます。
高原の湿地に生える植物を栽培しています。春にはミズバショウやコガネミズバショウ、初夏にはニッコウキスゲが群落で咲きます。木道橋を渡り、植物に囲まれながら写真撮影も可能。また、夏には近辺でキレンゲショウマも咲き、お客様をお出迎えます。

Rhododendron pentaphyllum var. nikoense

Epimedium grandiflorum var. thunbergianum

Shortia uniflora

Phyllodoce caerulea

Caltha palustris var. enkoso

Trillium smallii

Viburnum furcatum

Prunus sargentii

Erythronium japonicum

Larix kaempferi

Anemone pseudo-altaica

Lysichiton americanum

Rhododendron reticulatum

Heloniopsis orientalis

Glaucidium palmatum

Jeffersonia dubia

Geum pentapetalum

Clintonia udensis

Corylopsis spicata

Trillium erectum

Narcissus bulbocodium

Anemone flaccida

Scopolia japonica

Gentiana thunbergii

Ajuga incisa

Rhododendron keiskei

Rhododendron arboreum

Amana latifolia

Adonis amurensis

Primula denticulata

Pulsatilla vulgaris

Hepatica nobilis var. japonica

Lysichiton camtschatcense

Loiseleuria procumbens

Syneilesis palmata

Chelidonium japonicum
 アカヤシオ
Rhododendron pentaphyllum var. nikoense
4月中旬 ― 4月下旬
アカヤシオ
Rhododendron pentaphyllum var. nikoense
4月中旬 ― 4月下旬
 イカリソウ
Epimedium grandiflorum var. thunbergianum
4月中旬-5月上旬
イカリソウ
Epimedium grandiflorum var. thunbergianum
4月中旬-5月上旬
 イワウチワ
Shortia uniflora
4月中旬-4月下旬
イワウチワ
Shortia uniflora
4月中旬-4月下旬
 エゾノツガザクラ
Phyllodoce caerulea
4月下旬-5月上旬
エゾノツガザクラ
Phyllodoce caerulea
4月下旬-5月上旬
 エンコウソウ
Caltha palustris var. enkoso
4月上旬-5月中旬
エンコウソウ
Caltha palustris var. enkoso
4月上旬-5月中旬
 エンレイソウ
Trillium smallii
3月下旬-4月中旬
エンレイソウ
Trillium smallii
3月下旬-4月中旬
 オオカメノキ
Viburnum furcatum
4月下旬-5月上旬
オオカメノキ
Viburnum furcatum
4月下旬-5月上旬
 オオヤマザクラ
Prunus sargentii
4月中旬-5月上旬
オオヤマザクラ
Prunus sargentii
4月中旬-5月上旬
 カタクリ
Erythronium japonicum
3月下旬-4月中旬
カタクリ
Erythronium japonicum
3月下旬-4月中旬
 カラマツ
Larix kaempferi
4月下旬-5月上旬
カラマツ
Larix kaempferi
4月下旬-5月上旬
 キクザキイチゲ
Anemone pseudo-altaica
3月下旬-4月上旬
キクザキイチゲ
Anemone pseudo-altaica
3月下旬-4月上旬
 コガネミズバショウ
Lysichiton americanum
4月下旬-5月上旬
コガネミズバショウ
Lysichiton americanum
4月下旬-5月上旬
 コバノミツバツツジ
Rhododendron reticulatum
4月下旬-5月上旬
コバノミツバツツジ
Rhododendron reticulatum
4月下旬-5月上旬
 ショウジョウバカマ
Heloniopsis orientalis
3月中旬-4月中旬
ショウジョウバカマ
Heloniopsis orientalis
3月中旬-4月中旬
 シラネアオイ
Glaucidium palmatum
4月中旬-4月下旬
シラネアオイ
Glaucidium palmatum
4月中旬-4月下旬
 タツタソウ
Jeffersonia dubia
4月中旬-4月下旬
タツタソウ
Jeffersonia dubia
4月中旬-4月下旬
 チングルマ
Geum pentapetalum
4月下旬-5月上旬
チングルマ
Geum pentapetalum
4月下旬-5月上旬
 ツバメオモト
Clintonia udensis
4月下旬-5月上旬
ツバメオモト
Clintonia udensis
4月下旬-5月上旬
 トサミズキ
Corylopsis spicata
4月中旬-4月下旬
トサミズキ
Corylopsis spicata
4月中旬-4月下旬
 トリリウム・エレクタム
Trillium erectum
4月下旬-5月上旬
トリリウム・エレクタム
Trillium erectum
4月下旬-5月上旬
 ナーシサス・バルボコディウム(フエフキスイセン)
Narcissus bulbocodium
4月下旬-5月上旬
ナーシサス・バルボコディウム(フエフキスイセン)
Narcissus bulbocodium
4月下旬-5月上旬
 ニリンソウ
Anemone flaccida
4月中旬-4月下旬
ニリンソウ
Anemone flaccida
4月中旬-4月下旬
 ハシリドコロ
Scopolia japonica
4月中旬-4月下旬
ハシリドコロ
Scopolia japonica
4月中旬-4月下旬
 ハルリンドウ
Gentiana thunbergii
4月中旬-5月上旬
ハルリンドウ
Gentiana thunbergii
4月中旬-5月上旬
 ヒイラギソウ
Ajuga incisa
4月下旬-5月上旬
ヒイラギソウ
Ajuga incisa
4月下旬-5月上旬
 ヒカゲツツジ
Rhododendron keiskei
4月中旬-4月下旬
ヒカゲツツジ
Rhododendron keiskei
4月中旬-4月下旬
 ヒマラヤのシャクナゲ(ロードデンドロン・アルボレウム)
Rhododendron arboreum
4月下旬-5月上旬
ヒマラヤのシャクナゲ(ロードデンドロン・アルボレウム)
Rhododendron arboreum
4月下旬-5月上旬
 ヒロハノアマナ
Amana latifolia
4月上旬-4月中旬
ヒロハノアマナ
Amana latifolia
4月上旬-4月中旬
 フクジュソウ
Adonis amurensis
3月下旬-4月上旬
フクジュソウ
Adonis amurensis
3月下旬-4月上旬
 プリムラ・デンティキュラータ(タマザキサクラソウ)
Primula denticulata
4月中旬-4月下旬
プリムラ・デンティキュラータ(タマザキサクラソウ)
Primula denticulata
4月中旬-4月下旬
 プルサティラ・ブルガーリス(セイヨウオキナグサ)
Pulsatilla vulgaris
4月中旬-5月上旬
プルサティラ・ブルガーリス(セイヨウオキナグサ)
Pulsatilla vulgaris
4月中旬-5月上旬
 ミスミソウ
Hepatica nobilis var. japonica
3月下旬-4月中旬
ミスミソウ
Hepatica nobilis var. japonica
3月下旬-4月中旬
 ミズバショウ
Lysichiton camtschatcense
4月上旬-4月中旬
ミズバショウ
Lysichiton camtschatcense
4月上旬-4月中旬
 ミネズオウ
Loiseleuria procumbens
4月下旬-5月上旬
ミネズオウ
Loiseleuria procumbens
4月下旬-5月上旬
 ヤブレガサ
Syneilesis palmata
4月下旬-5月上旬
ヤブレガサ
Syneilesis palmata
4月下旬-5月上旬
 ヤマブキソウ
Chelidonium japonicum
4月下旬-5月上旬
ヤマブキソウ
Chelidonium japonicum
4月下旬-5月上旬
![]()
山上施設
![]()
レストラン・カフェ
![]()
ショップ
![]()
車イス優先トイレ
![]()
ベビールーム
![]()
駐車場
![]()
六甲山上バス乗車所
![]()
I.C./JCT
![]()
マップ内にあるスポット情報をカテゴリ別一覧で見ることができます。チェックボックスをON/OFF(表示/非表示)すると見やすく確認できます。
![]()
このマップをSNSやメールでシェアすることができます。
![]()
Googleマップ上で、大きく表示できます。スマートフォンでご覧になられている方はこちらで見ると便利です。